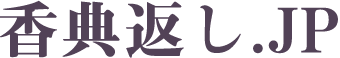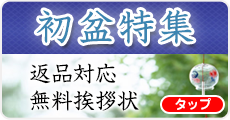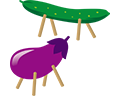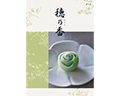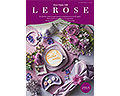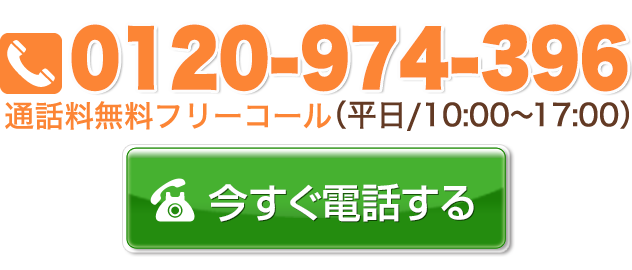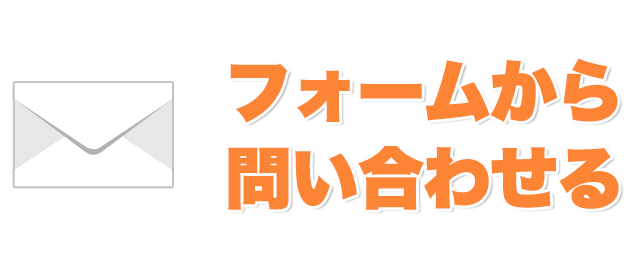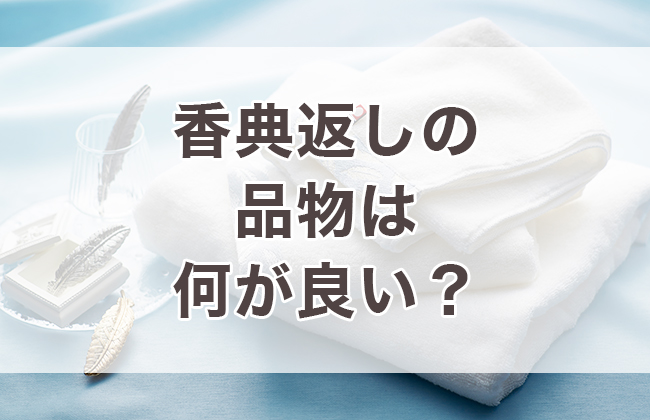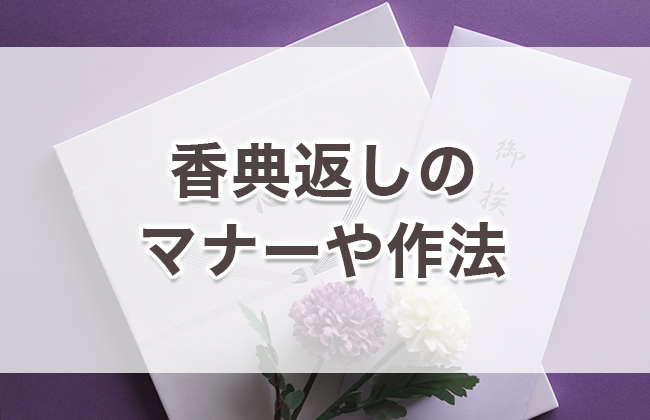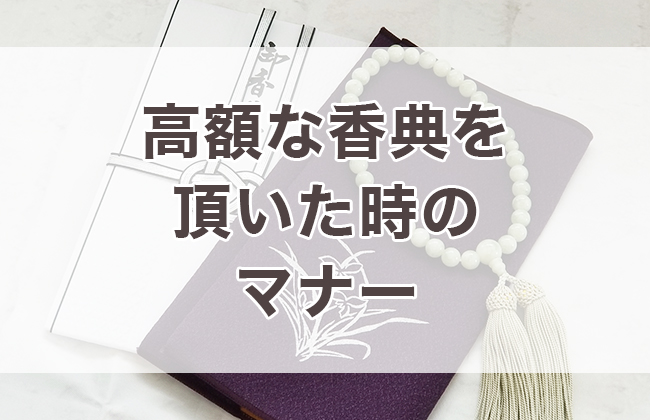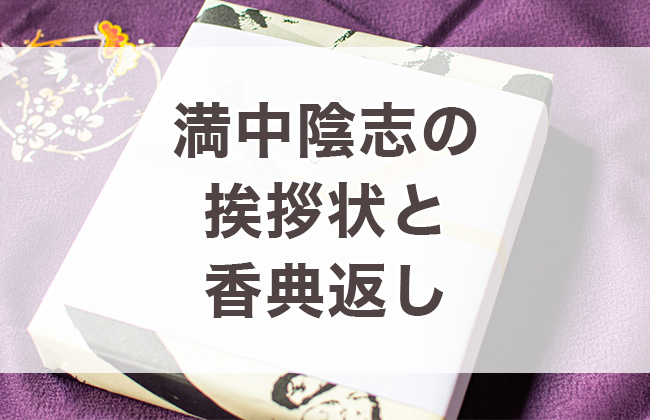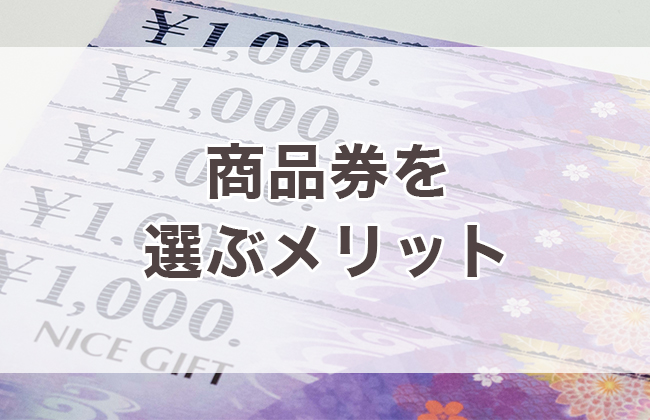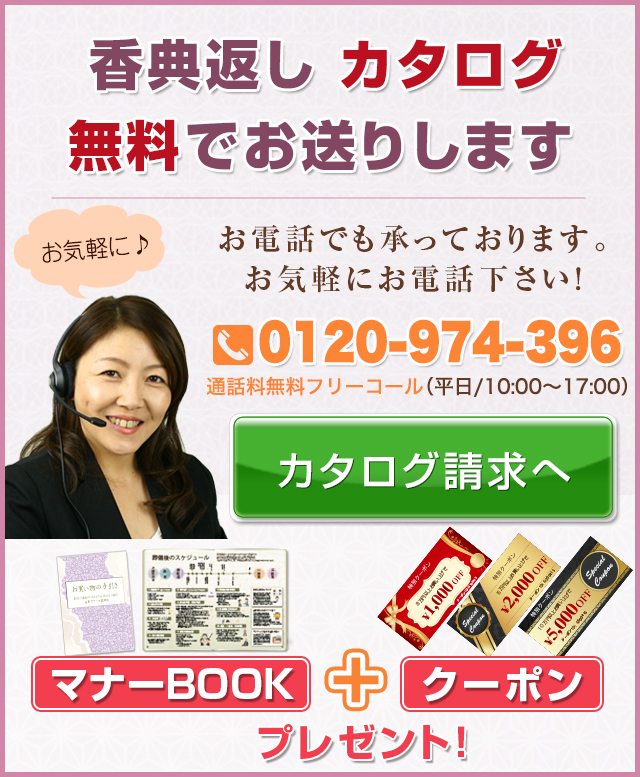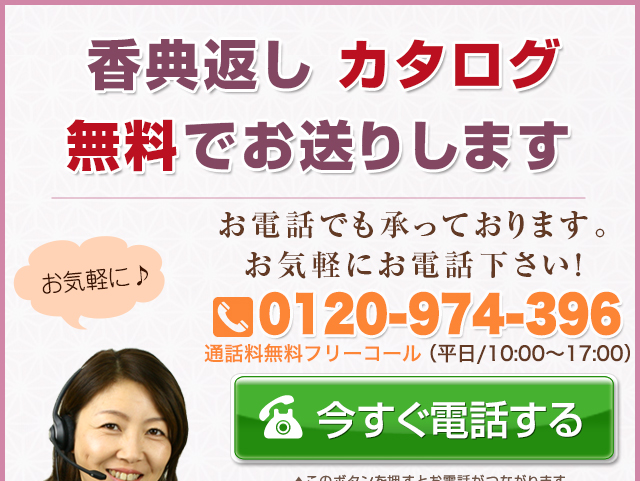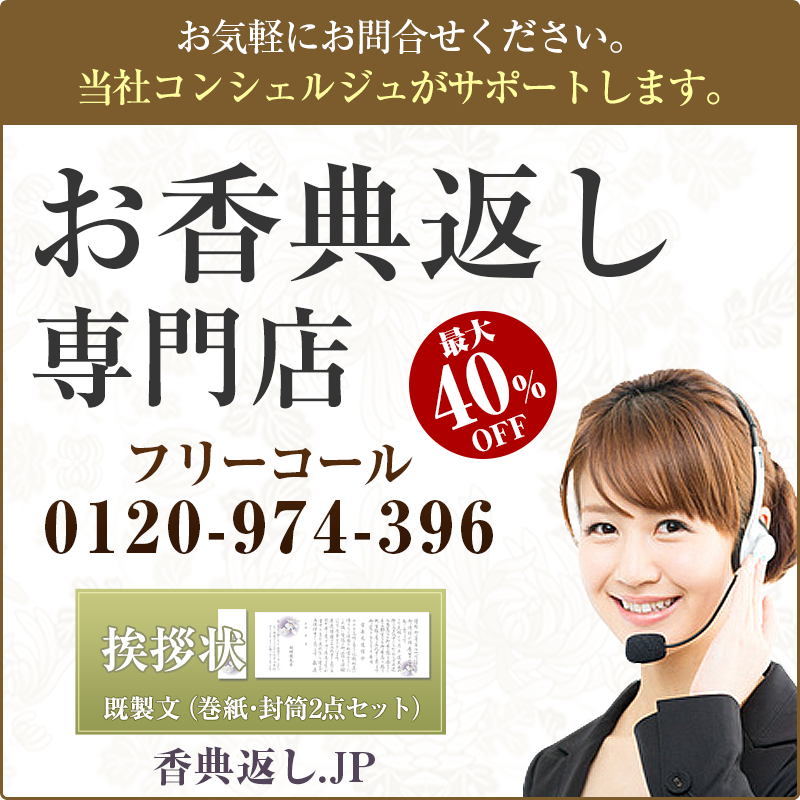香典返しに添える手紙やお礼状には様々なルールやマナーが存在します。送る相手に失礼にならないためだけではなく、故人が胸を張れるようにしっかりとマナーを守って心のこもったお礼状を作成してくださいね。
香典返しに添える手紙を書く時
香典返しにお礼状は必須?
葬儀に参列し、香典を頂いた方へ感謝の気持ちを込めて贈る「香典返し」。本来、香典返しは四十九日の忌明け後に直接相手をお伺いして、感謝の言葉と共に手渡しするのが慣例でした。しかし全国から参列者が訪れる現在では香典返しの品物は宅配便などを利用して郵送するのが一般的となっていますので、本来直接お伝えするべき感謝の言葉を手紙に書いて、品物に添えてお贈りするのが香典返しにおける大切なマナーとなっています。

親しい間柄の相手であれば品物を送る前にお電話などで挨拶することもあるかと思いますが、そのような場合でも改めて挨拶状を作成して、品物と一緒に送るのが自然でしょう。また、現在では手渡し・郵送に関わらず品物には挨拶状を添えた方が良いとされていますので、「香典返しには挨拶状は必須」と思っておいた方がいいですね。
当日返しの場合は?
香典返しを贈るのは四十九日の忌明け後とされていますが、近年では葬儀当日に品物をお渡しする「即返し」「当日返し」と呼ばれる習慣が浸透してきています。当日返しの場合は葬儀に参列して頂いた方に「会葬礼状」をお渡ししますので、こちらに香典のお礼も含めてしまう場合が多いようです。
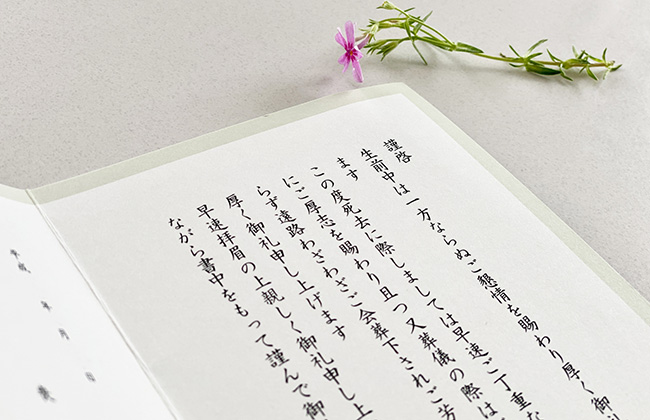
ただし、当日お渡しする香典返しの相場以上の高額な香典を頂いて、忌明け後に改めてお返しの品物を贈る場合は、やはりお礼状を添えて贈るのがマナーです。また、お礼状には「法要を無事に済ませた報告」や「戒名の報告」の意味もありますので、当日返しの場合でも、忌明け後に改めて挨拶状を送るとより丁寧な印象になりますね。
挨拶状の基本的な内容と文例
香典返しに添える挨拶状の基本的な内容、構成は以下の通りです。
- 葬儀に参列していただき、香典を頂いた事に対するお礼
- 戒名と四十九日の法要を滞りなく済ませたことの報告
- 生前の故人とのおつきあいに対するお礼
- 香典返しの品物を贈ることの報告
- 書面という略儀で済ませることへのお詫び
それでは実際にどのような文面になるのか、挨拶状の文例をご紹介します。
拝啓 先般 亡父○○ 葬儀に際しましては
ご多忙中にもかかわらず
ご丁寧なお心遣いを賜り誠にありがとうございました
お陰をもちまして
〇月〇日に四十九日忌の法要を相営むことができました
生前に故人が賜りましたご厚誼に改めて感謝申し上げます
つきましては 供養のしるしに心ばかりの品物をお届けいたしましたのでお納めくださいませ
本来であれば拝眉の上ご挨拶申し上げるべきとは存じますが 略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます
敬具

普段使う機会が少ない言葉や言い回しが多いので、まずは文例を参考にして作成してみるといいでしょう。親しい間柄の方への挨拶状であれば、もう少し砕けた表現や一般的な言い回しを使用しても問題ありません。
下記に相手別の文例、会社関係者への文例など複数の文例集をご用意しています。手書きで挨拶状を作成する際の参考にしてください。
お礼状を書くときの注意点
香典返しのお礼状を書くに当たり、いくつか守らなければならないルールがあります。香典返しに限らず様々な贈り物に添える挨拶状にも共通する場合がありますので、この機会に覚えてしまいましょう。
- 季節の挨拶は必要ない
香典返しの挨拶状では本題を簡潔に述べるべきとされていますので季節の挨拶は必要ありません。「拝啓・敬具」などの頭語・結語はあってもなくても構いません。 - 句読点は使用しない
法事が滞りなく済むようにという意味を込めて文章が途切れる句読点は使わない、句読点は相手が読みやすいように補助する役割なので読む力がある相手に対しては失礼にあたる、などの説があります。句読点を使用せず、改行や空白を適切に利用して読みやすさを確保するのがポイントです。 - 重ね言葉、忌み言葉は使用しない
「ますます」「いよいよ」「再び」「続く」などの言葉は「不幸が重なる、続く」を連想させるため縁起が悪いとされています。「重ねて」「再度」「改めて」など、別の表現に言い換えましょう。また、同じ理由で封筒を使用する場合も二重封筒ではなく一重のものを使用します。

次に、よくある間違いと正しい内容を見ていきましょう。
- 故人の続柄の記載ミス
故人の続柄は読み手に故人との関係性を明確に伝えるために重要です。間違えて記載すると失礼にあたる可能性があります。喪主から見た続柄を記載します。「父 〇〇」「母 〇〇」など、敬称はつけません。 - 文字の色とフォント
弔事の挨拶状はインクの色やフォントにも配慮が必要です。色付きのインクや派手なフォントを使用してはいけません。黒色のインク(活字の場合は墨色)で、楷書体や行書体など読みやすく落ち着いたフォントを使用します。手書きの場合は毛筆または筆ペンを使用するのが丁寧です。また「黒色のインク」が基本ですが薄墨(うすずみ)を使用する地域もあります。薄墨は「涙で墨が薄くなった」という意味を持ち、弔事で伝統的に使われます。 - 香典返しを辞退された方への配慮
香典返しを辞退された方にも挨拶状を送るのがマナーです。この場合、香典返しの品は送らず、感謝の気持ちを伝える手紙のみを送ります。辞退の理由(喪主の負担軽減など)に配慮し、「ご厚意に感謝する文面」にすることが重要です。
言葉遣いの間違い
- 「ご冥福をお祈りします」
×多くの宗教で用いられる一般的な弔意表現として使われる
〇全ての宗派で通用する表現ではなく、浄土真宗では使用しない - 「お疲れ様でした」
×職場などで使う表現であり、弔事の文面にはふさわしくない
〇弔事の場では感謝の気持ちを表す言葉の方が適切のため「ありがとうございました」が望ましい - 「亡くなりました」
×日常的で軽い言い方であり、あらたまった文書には適していない
〇丁寧な表現の方が好ましいため「逝去いたしました」「永眠いたしました」を使用する
構成の間違い
- 順序の間違い
×香典返しの報告を最初に書く
〇感謝→法要報告→香典返しの報告が一般的な順序。状況によって柔軟に対応する必要がある - 内容の重複
×同じ感謝の言葉を繰り返す
〇各段落で異なる内容を簡潔に表現するのがポイント - 必要事項の漏れ
×法要日程の記載忘れ
〇チェックリストを使用して確認を
これらの間違いに注意することで、故人を偲ぶ気持ちと参列者への心遣いがより伝わる挨拶状を作成することができます。
戒名・俗名の記載方法とその意味
香典返しに添える挨拶状では単に感謝の気持ちを伝えるだけでなく、故人に関する大切な情報を相手に正しくお知らせする役割も担っています。その中でも特に重要とされるのが、戒名(法名・霊名など)の記載です。ご芳志への御礼と、無事に忌明けを済ませたことをご報告する大事なものです。戒名を記載することには以下のような意味があります。
- 故人の仏弟子としての位階を示す
- 故人を弔い、供養する際の呼び名を関係者に伝える
- 故人の死後の身分を示す
- 今後の供養や法要での呼び方の統一
戒名記載の具体例
戒名がある場合の文例: 先般 亡父○○(俗名) 戒名○○○○○○院居士 葬儀に際しましては
戒名なしの場合の文例: 先般 亡父○○ 葬儀に際しましては

宗派による違い
- 浄土真宗:一般的には「法名」を用いる。戒名とは異なる概念で、故人の霊格を示すもの。
- 日蓮宗:一般的には「法号」を用いる。戒名とは異なる概念で、故人の霊格を示すもの。
- 神道:戒名に相当するものは存在しない。故人の霊名を記す場合もある。
ハガキに印刷は失礼?
香典返しの挨拶状は奉書紙と呼ばれる和紙に筆で手書きし、封筒に入れて送るのが最も丁寧な作法と言えるでしょう。確かに手書きの方が心がこもっていると感じる方も多いのですが、現代ではハガキに印刷する方がむしろ一般的となっており、決して失礼という事はありません。
葬儀社や通販ショップに依頼して作成してもらう、ネット印刷で作成するという方法が現代では主流だと言えるでしょう。遺族にとっては慌ただしく、心身共に負担がかかる時期でもありますので、このような便利なサービスを上手に利用するのも方法の一つです。

ハガキではなくきちんと封筒に入れて送りたい場合は、奉書紙に直接印刷する、ハガキ大のカードに印刷して封筒に入れる、という方法があります。故人が生前特にお世話になった方には奉書紙に手書きした挨拶状を送るなど、相手によって使い分けてもいいでしょう。
宗教によって異なる書き方
香典返しに添える挨拶状のテンプレートなどは、多くの場合「香典」「法要」など仏教の言葉を使用しています。従って、宗教が異なる場合はこれらの言葉を宗教に応じて置き換える必要があります。代表的な例は「忌明けに対する表現」でしょう。
仏教の「四十九日法要」は神道では「五十日祭」、キリスト教では「追悼ミサ(カトリック)」、「召天記念日(プロテスタント)」となります。他には、仏式での「死去」を神式では「帰幽」、香典返しを「偲草」と表現する、などが挙げられます。
また、近年では故人の遺志や経費を抑える為など様々な理由から、無宗教で葬儀を行うケースも増えています。間違った言葉を使ってしまわないか心配な場合は葬儀社などのプロに依頼して、宗教に対応したお礼状を作成してもらった方が無難だと言えるでしょう。当店では宗教別に挨拶状のご用意をしております。
下記に宗教別の文例集をご用意しています。挨拶状を作成する際の参考にしてください。
挨拶状の送付マナーとタイミング
香典返しの挨拶状は、いつ、どのように送るかといったマナーも非常に重要です。適切なタイミングと方法で送ることで、感謝の気持ちがより丁寧に伝わります。香典返しの挨拶状は基本的に四十九日の忌明け法要後、1ヶ月以内を目安に送るのが一般的です。これは仏教における忌明けの節目を大切にするためです。
- 即日返し(当日返し)の場合
葬儀当日に香典返しをお渡しした場合でも、後日改めて挨拶状を送るのがより丁寧です。特に高額な香典をいただいた方には品物だけではなく、改めて感謝の気持ちを伝える手紙を送るようにしましょう。 - 忌明けが遅れる場合
何らかの事情で四十九日の法要が遅れる場合でも、忌明け後に送るのが基本です。ただし、故人の命日や葬儀から時間が経ちすぎると、相手も状況を把握しにくくなるため、事前に連絡を入れるなどの配慮も検討しましょう。
封筒の選び方と表書き
香典返しの挨拶状は、封筒に入れて送ります。選び方や表書きにもマナーがあります。
- 封筒の選び方
一重の白無地封筒を選びます。二重封筒は「不幸が重なる」という意味合いから避けるべきという考え方があるためです。郵便番号枠のないものが正式とされますが、現在は郵便番号枠のあるものでも問題ありません。 - 表書き
封筒の表には「ご挨拶」や「お礼状」など、簡潔な表書きをするのが一般的です。裏には、差出人(喪主の氏名と住所)を記載します。
切手の選び方
香典返しの挨拶状を送る際の切手にも配慮が必要です。基本的には普通切手で問題ありませんが、絵柄に注意しましょう。華やかなキャラクターものや縁起の良い絵柄は避けるべきです。華やかすぎない落ち着いた花柄や風景の切手を使うのが一般的です。また、郵便局では「弔事用切手」として胡蝶蘭の切手を販売しています。

同封する品物
香典返しの品物と一緒に挨拶状を同封します。品物は香典の半額程度を目安とする「半返し」が一般的ですが、地域や関係性によって異なります。
のし(掛け紙)
香典返しには「のし」ではなく「掛け紙」を使用します。表書きは「志」または「満中陰志」(関西地方などで使用)とします。水引は黒白・紫銀の結び切り(二度と繰り返さないという意味合い)の水引を使用します。関西地方など、黄銀の結び切りの水引を使用する地域もあります。名前は喪主の氏名または「〇〇家」とします。
手渡しの場合のマナー
香典返しを直接手渡しする場合でも、挨拶状を添えるのが丁寧です。「このたびはご丁寧にありがとうございました」といった言葉を添え、品物と挨拶状を渡します。挨拶状の内容と、手渡しの際の言葉に矛盾がないようにしましょう。
香典返しの挨拶状は感謝の気持ちを伝える大切なツールです。これらのマナーを守り、真心を込めて作成することで故人への感謝と参列者への心遣いがより一層伝わるでしょう。
挨拶状のよくある質問
香典返しの挨拶状に関するよくある質問とその回答を紹介します。
Q.香典返しは必ず必要ですか?香典返しをしない場合でも挨拶状は必要ですか?
A.基本的には香典をいただいた場合、香典返しをするのが礼儀です。ただし、以下のような場合は香典返しをしないこともあります。
- 故人の遺志やご遺族の意向で辞退する場合:葬儀の際に「香典返し辞退」の旨を伝えている場合。
- 高額な香典をいただいた場合:相応の香典返しをするとかえって相手に負担をかける場合や、一部を寄付する場合など。
- 会社や団体からの福利厚生の一環である場合:香典が福利厚生費から出ている場合など。
香典返しをしない場合でも、香典をいただいたことへの感謝を伝える挨拶状は必要です。この場合、挨拶状には「お心遣いのみを頂戴いたしました」といった文言や、香典返しを辞退されたことへの感謝の気持ちを記します。
Q.挨拶状は手書きと印刷、どちらが良いですか?
A.手書きの方が丁寧な印象を与えますが、印刷でもマナー違反にはなりません。高額の香典をいただいた方や親しい方には一言手書きで添えると丁寧です。
Q.挨拶状に故人の名前は必要ですか?
A.はい、誰の香典返しかを明確にするために故人の氏名と続柄を記載しましょう。一般的には喪主の氏名よりも前に、故人の氏名と続柄(例:「亡父〇〇」)を記載します。
Q.句読点を使わないのはなぜですか?
A.句読点を使わないのは日本の伝統的なマナーで「滞りなく」という意味を持つためです。読みやすさを保つためには改行や空白を活用しましょう。
Q.遠方の方への挨拶状も同じで良いですか?
A.基本は同じですが、遠方から足を運んでくださったことに対する感謝の一文を添えるとより丁寧です。

Q.「薄謝」という言葉は使えますか?
A.「薄謝(はくしゃ)」は報酬に対する言葉で、香典返しには不適切です。「心ばかりの品」などの表現を使いましょう。
Q.即日返し(当日返し)や忌明け前、法要日が未定のうちに香典返しを送る場合は?
A.略式のお礼状を添えて先に香典返しを送り、後日正式な挨拶状を改めて送ると丁寧です。
Q.職場から連名で香典をいただいた場合、どう対応すべきですか?
A.個別返しかまとめて返すかは金額や職場の慣習に応じて判断します。挨拶状も個別または部署宛てで作成します。
Q.挨拶状を送り忘れた場合はどうすればよいですか?
A.気づいた時点で速やかに送付しましょう。遅れた理由を簡潔に添えて、お詫びの文言を入れることが大切です。
Q.宗教が不明な場合、どんな表現を使えばいいですか?
A.一般的な仏教式の表現を使用するか、宗教色の少ない表現を選ぶことが無難です。「永眠」「お返し」「感謝」などの言葉は宗教を問わず使用できます。
Q.挨拶状の文字数に決まりはありますか?
A.特に決まりはありませんが、400字程度、A4用紙1枚が目安です。簡潔に要点を押さえましょう。
Q.海外在住の方への香典返しはどう対応すべきですか?
A.海外への発送は時間がかかるため、事前に連絡を取ることが大切です。国際郵便の制限もあるので現地で購入できる商品券や、日本の品物を現地で受け取れるサービスを利用することも検討してください。
Q.挨拶状を印刷業者に依頼する際の注意点は?
A.誤字や忌み言葉の有無、戒名の正確さ、句読点の有無などを入念に校正しましょう。弔事に慣れた業者を選ぶと安心です。
Q.挨拶状の封筒はどのようなものが適切ですか?
A.白無地または薄いグレーの封筒が一般的です。柄や光沢のある封筒は避け、毛筆または筆ペンで丁寧に宛名を書きましょう。
Q.親族にも挨拶状は必要ですか?
A.はい、香典をいただいた場合は親族にも送るのが一般的です。より親しみやすい表現を使用しても構いません。
Q.個人的なメッセージを添えても良いですか?
A.親しい方であれば、思い出や感謝の気持ちを添えても構いません。ただし、文全体のバランスに注意しましょう。
相手別の文例集
香典返しの挨拶状は受け取る相手との関係性に応じて、文面のトーンや内容を調整することが大切です。こちらでは受け取る相手別に内容のポイントと文例を掲載しています。
親族向けの挨拶状
親族は故人やご遺族にとって最も身近な存在であり、葬儀においても様々な面で協力してくださったことでしょう。そのため、儀礼的な表現だけでなくこれまでの感謝と今後も変わらぬお付き合いをお願いする気持ちを込めた文面が望ましいです。親族に対しては、より親しみやすい表現を用いることができます。また、家族の近況や今後のお付き合いへの言及も適切です。
- やや砕けた表現の使用可能
- 家族の状況や今後の予定への言及
- 個人的なエピソードの挿入
- 継続的な関係性への配慮
この度は父の葬儀に際しご多忙の中お越しいただき
また過分なるお心遣いを賜り心より感謝申し上げます
お陰様で○月○日に四十九日の法要も無事に済ませることができました
父も皆様のお気持ちをきっと喜んでいることと存じます
心ばかりの品をお送りいたしますのでどうぞお納めください
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます
謹啓
先般 父○○が永眠いたしました際には ご多忙の中 遠路はるばるお運びいただき またご鄭重なるご厚志を賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができました
これもひとえに皆様の温かいお心遣いのおかげと 改めて感謝の念に堪えません
父が生前 皆様から賜りましたご厚情に深く感謝するとともに 今後は私どもがしっかりと家を守ってまいりますので 何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
時節柄 どうぞご自愛くださいませ
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
職場関係者向けの挨拶状
職場関係者に対しては、ビジネスマナーを重視した丁寧で簡潔な表現が求められます。個人的な感情を前面に出しすぎず、丁寧さを意識しましょう。
- 正式で丁寧な敬語の使用
- 簡潔で要点を押さえた内容
- 今後の業務への配慮表明
- 個人的すぎる内容は避ける
謹啓
先般 亡父○○ 葬儀に際しましては
ご多忙中にもかかわらずご丁寧なご弔慰を賜り
誠にありがとうございました
お陰をもちまして○月○日に四十九日忌の法要を
滞りなく相営むことができました
つきましては供養のしるしまでに心ばかりの品を
お送りいたしますのでご受納くださいませ
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます
謹白
謹啓
先般 私ども父○○の葬儀に際しましては 公私とも大変お忙しい中 ご会葬ならびに温かいご厚志を賜り 誠にありがとうございました
おかげさまで 四十九日の法要も滞りなく済ませることができました
皆様のお心遣いに深く感謝申し上げます
本来であれば 直接お目にかかり御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶に代えさせていただきます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう お願い申し上げます
まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)

友人・知人向けの挨拶状
友人や知人に対しては、堅すぎず親しみやすい表現を心がけながらも、礼儀を保った内容にします。
- 温かみのある表現の使用
- 故人との思い出への言及可能
- より人間的な感情の表現
- 継続的な友情への言及
このたびは父の葬儀に際し
お忙しい中お越しいただき また温かいお心遣いをいただき 本当にありがとうございました
皆様のお気持ちに支えられ○月○日に 四十九日の法要も無事に終えることができました
父も長年にわたる皆様のご厚情を心から感謝していたことと思います
心ばかりの品をお送りいたします
今後ともどうぞよろしくお願いいたします
謹啓
このたびは 父○○の永眠に際しまして ご多忙の折にもかかわらず ご会葬賜り またご丁重なご厚志を頂戴し 誠にありがとうございました
心より御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を無事に執り行うことができました
皆様の温かいお心遣いに どれほど助けられたか分かりません
生前の父が皆様から賜りましたご厚情に 改めて深く感謝申し上げます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
宗教別の文例集
香典返しの挨拶状は故人の信仰していた宗教・宗派によって適切な表現が異なります。特に仏教以外の宗教では「忌明け」や「供養」といった言葉を使用しないため注意が必要です。ここでは各宗教・宗派に合わせた挨拶状の書き方と文例をご紹介します。
■浄土真宗
浄土真宗では人は亡くなるとすぐに阿弥陀如来の力によって浄土に往生すると考えます。そのため「冥福を祈る」「供養」といった概念がなく、「忌明け」という考え方もありません。
- 「往生」「報恩感謝」などの言葉を使用する。
- 仏教用語(冥福、供養、忌明けなど)は避ける。
- 故人が浄土に往生したことを伝える。
謹啓
先般 父○○が永眠いたしました際には ご多忙の中 ご懇篤なるご厚志を賜り 誠にありがとうございました
おかげさまで 父は阿弥陀如来の慈悲により 無事に浄土に往生いたしました
これもひとえに皆様の温かいお心遣いのおかげと 報恩感謝の念に堪えません
本来であれば 直接お目にかかり御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶に代えさせていただきます
つきましては ささやかではございますが 報恩感謝のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
■日蓮宗
日蓮宗では、故人は即座に仏になると考えられています。四十九日は重要な法要ですが、感謝の気持ちを伝える文面は他の仏教宗派と大きくは変わりません。ただし、教義に沿った表現を心がけることが望ましいです。
- 「ご厚志」「ご懇篤なるご厚情」など、丁寧な言葉遣いをする。
- 「成仏」「回向」といった言葉を用いることも可能。
謹啓
先般 父○○が永眠いたしました際には ご多忙の中 ご会葬ならびに温かいご厚志を賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができました
皆様の温かいお心遣いに 改めて感謝の念に堪えません
父が生前 皆様から賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに 今後も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
■真言宗
真言宗も仏教の宗派であり、四十九日の忌明け法要後に香典返しを行うのが一般的です。文面も他の仏教宗派と大きな違いはありませんが、故人の冥福を祈る気持ちをより深く表現することが特徴です。
- 仏教の一般的な用語を使用する。
- 故人の冥福を祈る気持ちを丁寧に表現する。
謹啓
先般 私ども父○○が永眠いたしました際には ご多忙の中 ご会葬ならびに過分なるご厚志を賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができました
これもひとえに皆様の温かいご厚情の賜物と 深く感謝いたします
父が生前 皆様から賜りましたご厚情に改めて感謝申し上げますとともに 今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)

■天理教
天理教では人が亡くなることを「出直し(でなおし)」と捉え、魂は親神様のもとへ帰ると考えます。そのため「ご冥福をお祈りします」などの仏教用語は使用しません。
- 「出直し」という言葉を使用する。
- 仏教用語(冥福、供養、成仏、忌明けなど)は避ける。
- 「お慰め」や「励まし」への感謝を伝える。
謹啓
先般 父○○が親神様のお召しによって出直しいたしました際には ご多忙の中 遠路はるばるお運びいただき またご丁寧なご厚志を賜り 誠にありがとうございました
皆様からの温かいお言葉に どれほどお慰めと励ましをいただいたか分かりません
心より厚く御礼申し上げます
つきましては ささやかではございますが 感謝のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
■神道
神道では故人は「神様」になると考えられています。そのため仏教でいう「忌明け」は「五十日祭」にあたり、この時期に香典返しにあたる「偲び返し」を行います。「冥福」「供養」などの仏教用語は使用しません。
- 「帰幽(きゆう)」「五十日祭」などの神道用語を使用する。
- 「御霊のご平安をお祈りいたします」など、神道独自の表現を用いる。
- 仏教用語(冥福、供養、忌明けなど)は避ける。
謹啓
先般 父○○が帰幽いたしました際には ご多忙の中 ご会葬ならびに丁重なるご玉串料を賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に五十日祭の儀を滞りなく執り行うことができました
これもひとえに皆様の温かいお心遣いのおかげと 深く感謝しております
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
つきましては ささやかではございますが 偲びのしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
■キリスト教(カトリック)
キリスト教では故人は神のもとに召されると考えられ、葬儀は「告別式」ではなく「葬儀ミサ」などと呼ばれます。香典返しに相当する習慣はありませんが、香典にあたる献花料や御ミサ料をいただいた場合、感謝のお礼状を送るのが一般的です。
- 「召天(しょうてん)」や「神のもとに召されました」といった表現を用いる。
- 仏教用語(忌明け、冥福、供養など)は避ける。
- 「安らかな眠りをお祈りください」などの言葉は適切ではない(故人はすでに神のもとにいるため)。
- 「神の恵み」や「感謝」の言葉を織り交ぜる。
謹啓
先般 私ども父○○が神のもとに召されました際には ご多忙の中 葬儀ミサにご列席いただき また温かいお心遣いを賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
皆様からの温かいお言葉に どれほど励まされたか分かりません
深く感謝申し上げます
つきましては ささやかではございますが 感謝のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
■キリスト教(プロテスタント)
プロテスタントも、故人は神のもとに召されるという考え方はカトリックと同様です。カトリックとの違いは、儀式や呼称にあります。香典返しの習慣はありませんが、感謝のお礼状を送ります。
- 「召天」や「神のもとに召されました」といった表現を用いる。
- 仏教用語(忌明け、冥福、供養など)は避ける。
- 「感謝」の言葉を織り交ぜる。
謹啓
先般 父○○が神のもとに召されました際には ご多忙の中 ご葬儀にご列席いただき また温かいお心遣いを賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
皆様のお支えに どれほど感謝しているか計り知れません
つきましては ささやかではございますが 感謝のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
特殊なケースの文例集
香典返しの挨拶状を作成する際、通常のケースとは異なる状況に直面することもあります。ここでは特殊なケースにおける挨拶状の書き方と対応について解説します。
夫婦連名での挨拶状
夫婦で香典をいただいた場合や、喪主が夫婦で連名で挨拶状を送りたい場合もあります。
- 喪主の氏名の下に、配偶者の氏名を連名で記載する。
- 夫婦連名で感謝の気持ちを伝える文面にする。
謹啓
先般 私ども父○○が永眠いたしました際には ご多忙の中 ご会葬ならびに温かいご厚志を賜り 誠にありがとうございました
夫婦共々 心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができました
これもひとえに皆様の温かいお心遣いのおかげと 改めて感謝の念に堪えません
父が生前 皆様から賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに 今後とも私ども夫婦ともども 変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
妻〇〇
代理人による挨拶状
喪主が高齢であったり体調がすぐれないなどの理由で、挨拶状の差出人が喪主の代理人となる場合があります。この場合誰が代理人であるかを明確に記載し、代理人からの挨拶状である旨を伝えることが重要です。
- 喪主の名前を記し、その下に「(喪主の氏名)名代」または「(喪主の氏名)長男(または長女)〇〇」などと記載する。
- 喪主の状況を簡潔に述べる。
謹啓
先般 私ども父○○が永眠いたしました際には ご多忙の中 ご会葬ならびに過分なるご厚志を賜り 誠にありがとうございました
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
本来であれば 故人より直接御礼申し上げるべきところではございますが 生前病床にあり叶いませんでしたので 略儀ながら長男〇〇(または長女〇〇)が代わりましてご挨拶申し上げますこと 何卒ご容赦ください
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
書中にて御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)名代
長男〇〇

会社・団体からの香典への対応
会社や団体から香典をいただいた場合、個人からの香典とは異なる対応が必要です。特に連名で香典をいただいた場合は代表者の方宛に挨拶状を送り、必要に応じて個々の方々へもお礼を伝えるようにしましょう。
- 会社名・団体名を正確に記載する。
- 代表者の方宛に送る場合は、その旨を明記する。
- 個々の方々への感謝も忘れずに。
謹啓
このたびは 私ども父○○の永眠に際しまして 貴社(貴団体)の皆様よりご丁寧なご厚志を賜り 誠にありがとうございました
社員(会員)の皆様にも 心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができました
本来であれば 直接お目にかかり御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶に代えさせていただきます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう お願い申し上げます
まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
家族層向けの挨拶状
故人の配偶者や子など、ご家族として香典をくださった方々には連名で挨拶状を作成することもあります。家族としての感謝の気持ちを伝えましょう。
- ご家族連名での挨拶状とする。
- 故人への感謝と、家族としての決意を述べる。
- 今後の変わらぬご厚情をお願いする。
謹啓
先般 私ども父○○の永眠に際しましては 皆様より温かいご厚志を賜り 誠にありがとうございました
心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 去る○月○日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができ
ました
これもひとえに皆様のお力添えの賜物と 家族一同 深く感謝しております
父が生前 皆様から賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに 今後も家族一同 力を合わせて歩んでまいりますので 何卒変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
つきましては ささやかではございますが 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
まずは略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
妻〇〇
長男〇〇
長女〇〇
忌明け前の挨拶状
四十九日の忌明け法要前に香典返しを送る場合は通常、即日返しの場合に限られます。その際も、後日改めて忌明けの挨拶状を送るのが丁寧ですが、簡潔なお礼の手紙を添えることも可能です。
- 忌明け前である旨を明確にする。
- 略式である旨を伝える。
- 後日改めて挨拶状を送る可能性があることを示唆する。
謹啓
このたびは 父○○の永眠に際しまして ご会葬ならびに温かいご厚志を賜り 誠にありがとうございました
つきましては ささやかではございますが 心ばかりの品をお贈りいたしました
何卒ご受納いただければ幸いに存じます
本来であれば 忌明けの後に改めてご挨拶申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます
時節柄 どうぞご自愛くださいませ
謹白
令和○年○月○日
〇〇(喪主氏名)
まとめ
香典返しに添える挨拶状は単なる形式ではなく、故人を悼むお気持ちと参列者への深い感謝を丁寧に伝える大切なものです。宗教・相手との関係性・地域の慣習によって文面の表現やタイミング、言葉遣いには違いがありますが、最も大切なのは“心を込めて相手に伝える姿勢”です。
多くのルールやマナーに戸惑うこともあるかもしれませんが、故人が安心して旅立てるように、また遺族の思いがきちんと伝わるように、ひとつひとつ丁寧に対応していきましょう。
誰に対しても失礼のない、そして故人にも胸を張れるような挨拶状を作成することが香典返しを通じた最後の「ご報告と御礼」になるはずです。
関連記事
葬祭マナーカテゴリ
- 香典返し
-
- カテゴリTOP
- 香典返しとは
- 香典返しと忌明けのあいさつ状
- 香典返しのマナーや作法について
- 香典返しの送る時期やマナーについて
- 香典返しを送る際のお礼状やマナー
- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います
- 香典返し挨拶状の文例などについて
- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて
- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント
- 香典返し「のし」について
- 香典返しの相場について
- 香典返しに商品券を選ぶメリット
- 香典返しを辞退する方法
- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー
- 香典返しの品物は何が良い?
- 香典返しでカタログギフトは失礼?
- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方
- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて
- 香典返しの時期と金額相場
- センスのいい香典返しを選ぶポイント
- 喪家・葬儀まで
- 弔問客
- 法要・供養
- 社葬