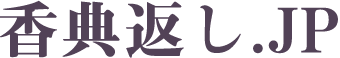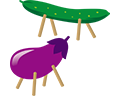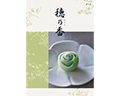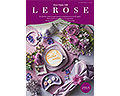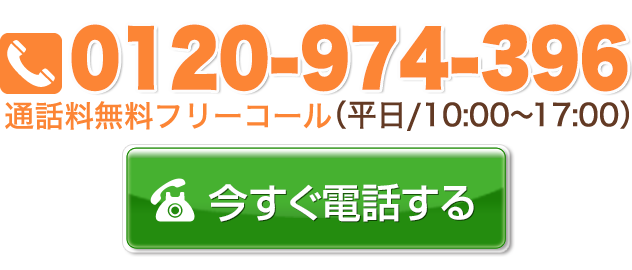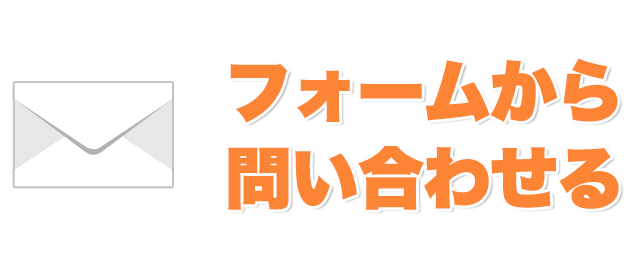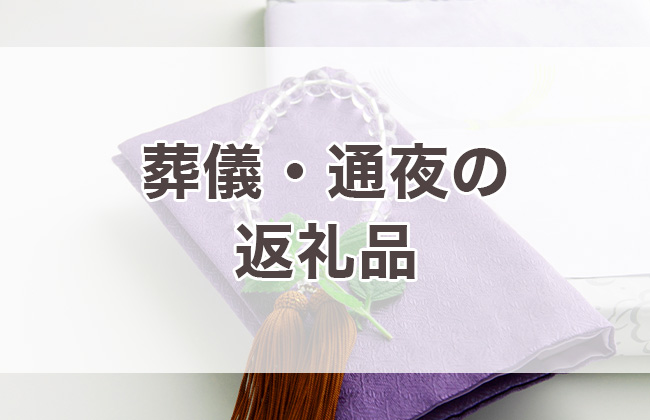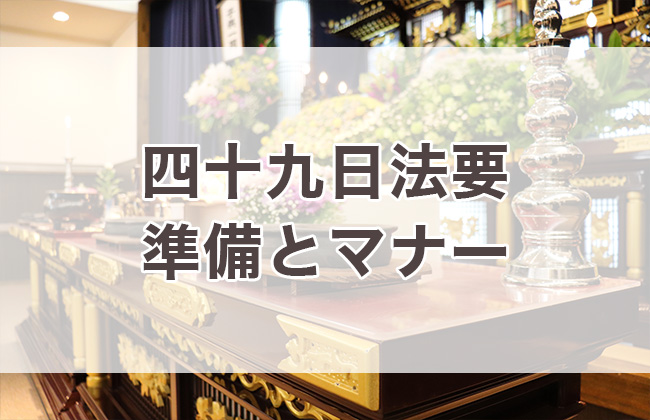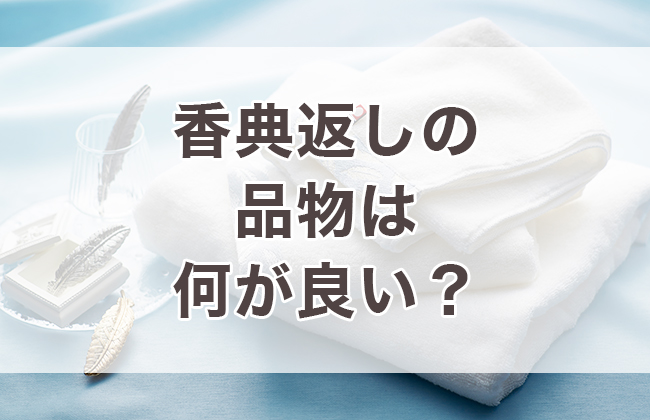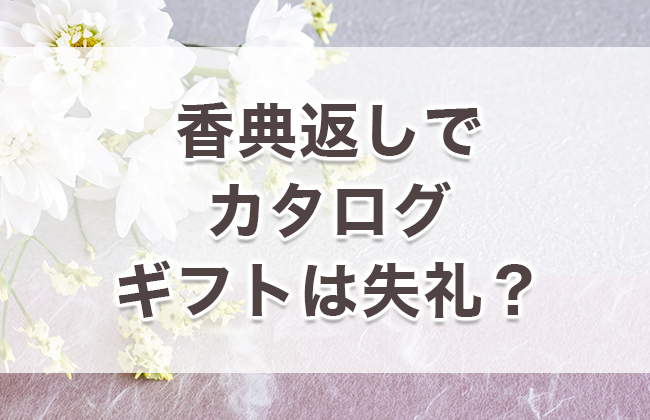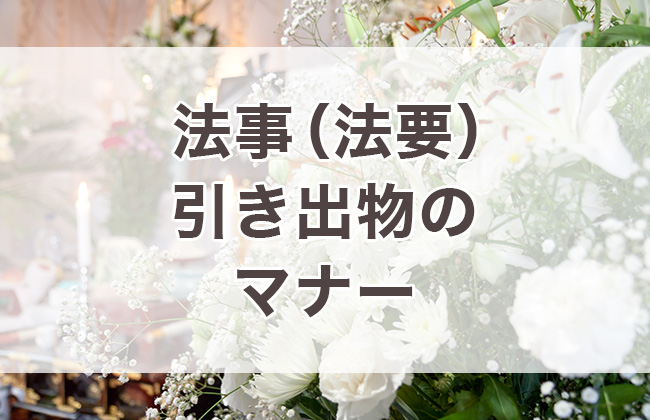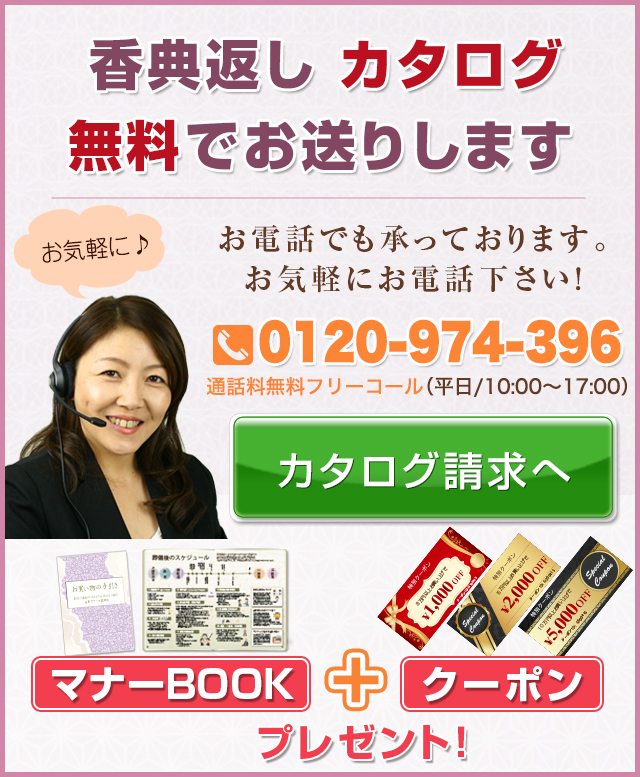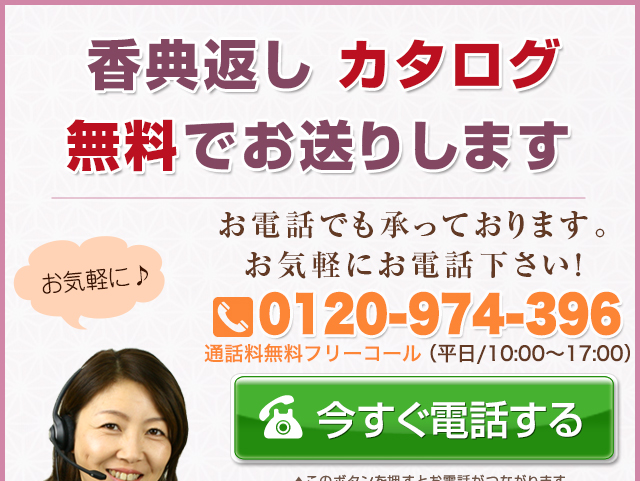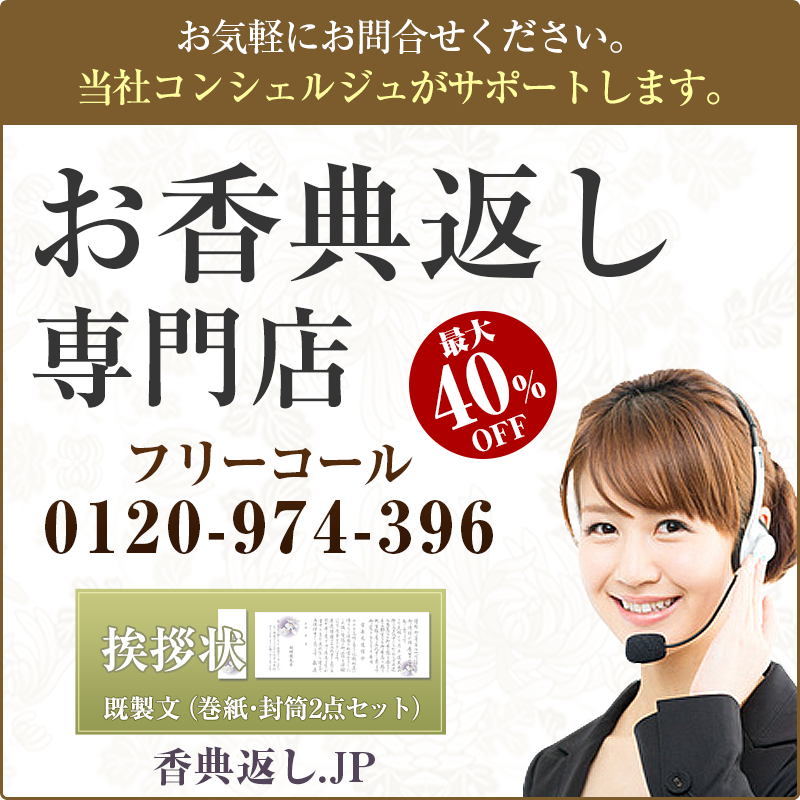葬儀や法要で参列者に贈る品物には様々な種類や呼び名がありますので混同してしまいがちです。しかし一度理解してしまえば簡単ですので、今回の記事を参考に、基本的な知識を身に着けておきましょう。
四十九日のお返し(引き出物)
香典返しと法要の引き出物の違いについて
香典返しと法要の引き出物は、どちらも四十九日に関連する「お返し」ですが、その性質や目的には明確な違いがあります。
香典返しは、葬儀の際に香典(弔問金)を持参して参列してくれた方へのお礼として贈る品物です。具体的な特徴は以下の通りです:
- 対象者: お通夜や葬儀に参列し、香典を包んでくれた方々
- お礼の理由: 香典(金銭的なお見舞い)に対するお返し
- 金額の目安: 頂いた香典の30%〜50%程度(地域によって異なる)
- 伝統的なタイミング: 四十九日の忌明け後に贈るのが古来からの習慣
- 近年の傾向: 「即日返し」や「当日返し」として葬儀当日に渡すことも増えている
香典返しは弔問に対するお礼という性質から、故人との関係性や頂いた香典の金額に応じて、返礼品の内容や価格帯を変えることが一般的です。
法要の引き出物は、四十九日法要に参列し、お供え物をしてくれた方へのお礼として贈る品物です。特徴は以下の通りです:
- 対象者: 四十九日法要に参列し、お供え物や御霊前を持参した方々
- お礼の理由: 法要参列とお供え物に対するお礼
- 金額の目安: 一般的には3,000円〜5,000円程度で一律の場合が多い
- タイミング: 法要当日の会食後、または会食の席で渡すことが多い
- 選び方の特徴: 参列者全員に同じものを準備することが多い
法要の引き出物は、法要という儀式への参列に対する感謝の意味合いが強く、故人を偲ぶ場に集まってくれたことへのお礼という性質があります。

実際の対応例としては以下のようなケースがあります:
- ケース1: 葬儀に参列し香典を包み、四十九日法要にも参列してお供えした方 → 香典返し + 法要の引き出物
※葬儀当日に「当日返し」として香典返しを済ませている場合は、四十九日時点で新たに香典返しを行う必要はなく、法要の引き出物のみでOKです。 - ケース2: 葬儀には参列せず香典のみ送った方で、四十九日法要にも参列しない方 → 香典返しのみ(郵送などで対応)
- ケース3: 葬儀には参列せず、四十九日法要のみ参列した方 → 法要の引き出物のみ
香典返しと法要の引き出物の違いを正しく理解することで、失礼のない適切なお返しができるようになります。地域の習慣や家庭の方針も考慮しながら、故人を偲ぶ大切な儀式に参列してくださった方々への感謝の気持ちを形にしましょう。
四十九日のお返しを準備する手順
四十九日のお返しの準備は、法要の1〜2週間前から始めるのが理想的です。以下の手順を参考に、計画的に進めていきましょう。
- 参列者リストの作成: まず、四十九日法要に参列予定の方々のリストを作成します。当日参列できない方で後日郵送する方も含めて、正確な人数を把握しておきましょう。
- 予算の設定: 参列者の人数に基づいて、全体の予算を決めます。地域の習慣や参列者との関係性を考慮して、1人あたりの金額を決定します。
- 品物の選定: 予算内で全員に同じ品物を用意するか、関係性によって品物を分けるか検討します。実用的で持ち帰りやすいものを中心に選びましょう。
- 注文・手配:必要な数量を確認のうえ、スケジュールに十分な余裕を持って注文・手配します。特に人気商品や季節商品は、時期によっては早々に在庫がなくなることもあるため、できるだけ早めのご注文をおすすめします。納期に余裕を持つことで、万が一のトラブルにも柔軟に対応でき、安心です。
>>当店のお届けまでの目安はこちら
- かけ紙(のし紙)・包装の指定: 注文時に「志」または「粗供養」の表書きと、黒白または関西では黄白の結び切りの水引を指定します。
- 挨拶状の準備: 郵送する場合は特に、心のこもった挨拶状を準備しておきましょう。
>>当店のかけ紙・挨拶状についてはこちら
- 当日の準備: 法要当日に渡す場合は、誰にどの品物を渡すか混乱しないよう、リストと照らし合わせて確認しておきます。
この準備を計画的に進めることで、当日の混乱を避け、故人を偲ぶ大切な四十九日法要をスムーズに執り行うことができるでしょう。
相場(金額の目安)
法要の引き出物は会食費を含めて全返しする場合、会食費と引き出物を合わせて半返しとする場合など、地域によって習慣が大きく異なりますが、一般的には3,000円~5,000円程度を目安に品物を用意すれば良いと言われています。

四十九日のお返しは基本的に法事の当日にお渡しするものですので、お供えの額を確認してから品物を用意することはできません。従って、頂いた金額にかかわらずに一律同じ金額の品物を用意するケースが多いのです。
このような仏事は地域や親族によって考え方、習慣が大きく異なります。習慣にそぐわないお返しをすることで失礼と感じられてしまう可能性も否定できません。金額相場はあくまで目安として参考にする程度にとどめ、事前にその地域の習慣をよく知る方に相談しておいた方が確実と言えるでしょう。
喜ばれる品物の選び方
四十九日のお返しに最適な品物選びは、参列者の年齢や関係性、実用性などを考慮することが大切です。定番の人気商品から年代別のおすすめ品、お菓子選びのポイントまで詳しくご紹介します。

法事の引き出物で定番とされているのは、食べたら無くなる食品類や使えばなくなる消耗品など、いわゆる「消えもの」と呼ばれるものです。海苔、コーヒーやお茶、調味料、タオル、洗剤などが昔から法要の引き出物に選ばれてきました。
当日持ち帰りやすいように軽くてかさばらないものや、日持ちのするもの、日常使える実用品が喜ばれる引き出物として人気を集めています。タオルや寝具、バスグッズなどは普段使いのものよりも少し質の高いものを選ぶと、喜んでもらえる贈り物になるのではないでしょうか。近年では贈った相手が好きなものを選べるカタログギフトが選ぶ側の負担も少なく、一番人気の引き出物です。弔事専門のカタログギフトなら、世代や性別を選ばずどなたにも贈れますのでおすすめですよ。
以下に、年代別のおすすめ品をご紹介します。
高齢の方向け
- 日本茶やコーヒーのギフトセット: 毎日の習慣に取り入れやすく、実用的です
- 健康食品: 高級な梅干しや昆布、緑茶などの健康に良い食品は特に喜ばれます
- 和菓子詰め合わせ: 伝統的な和菓子は高齢の方に親しみやすいものです
中年層向け
- 調味料ギフト: 高級醤油や調味料のセットは日常使いできる実用的な贈り物です
- タオルセット: 上質なフェイスタオルやバスタオルのセットは喜ばれます
- カタログギフト: 自分で好きなものを選べる自由さが中年層には特に好評です
若年層向け
- スイーツギフト: 洋菓子や和洋折衷の菓子は若い世代に人気があります
- コーヒードリップパックセット: おしゃれで使いやすいドリップタイプは若い方に人気です
- キッチン消耗品: 調理器具や台所用品など、新生活に役立つアイテムを贈るのも良いでしょう
どのような品物を選ぶ場合でも、丁寧なかけ紙と落ち着いた包装を心がけ、感謝の気持ちをお伝えすることが最も大切です。
お返しを選ぶ際のNG集
四十九日のお返しを選ぶ際には、避けるべきものがいくつかあります。マナー違反とならないよう、以下のポイントに注意しましょう。
- 切れるもの・割れるもの: 包丁やハサミなどの「切れる」道具、ガラス製品などの「割れる」ものは、縁を切る・関係が割れるという連想から避けるべきです。
- 高価すぎる品物: 頂いたお供えの金額に対して著しく高額な品物は、相手に負担を感じさせる可能性があります。
- 華美な装飾のもの: 弔事のお返しですので、派手な色や装飾の施された品物は不適切です。
- 賞味期限の短いもの: 特に郵送する場合は、配送中に傷んでしまう可能性のある生菓子などは避けましょう。
- 重すぎる・かさばりすぎるもの: 参列者が持ち帰る際の負担になるため、特に高齢者がいる場合は配慮が必要です。
- 不吉な連想をさせるもの: 数字の「4」や「9」(死や苦を連想)を含むセットやデザインは避けましょう。
- 個人的過ぎる趣味性の強いもの: 故人や喪主の個人的な趣味に偏りすぎた品物は、受け取る側に合わない可能性があります。
これらのNGポイントを避け、参列者の立場や気持ちを考えた上で、感謝の気持ちが伝わる品物を選びましょう。
贈り方のマナー
四十九日のお返しを贈る際には、適切な時期や方法、かけ紙(のし紙)や挨拶状の作法など、守るべきマナーがあります。以下では、四十九日のお返しを贈る際の正しいマナーについて詳しくご説明します。

四十九日のお返しは、法要当日に渡す場合と後日郵送で贈る場合があります。当日お渡しする場合は法要後、もしくは法要の後の会食後にお渡しすることになります。施主が一人ひとりにお礼を伝えながら手渡しするのが一番良いのですが、会食の参加者が多く、会食後に一人ひとりお渡しするのが難しい場合は事前にそれぞれの席に準備しておく場合もあります。いずれにしても、丁寧に感謝の気持ちを述べてお渡しするようにしましょう。
ご霊前を頂いても、事情により法要に参列できないという方には後日郵送でお返しの品物を贈ります。きちんとお礼状を添え、法要の翌日から1か月以内を目安に相手にお届けできるように手配しておきましょう。ただし、四十九日のお返しは不祝儀となりますので、年始や相手のお祝い事がある時期は避けて贈るのがマナーですので気を付けて下さいね。
四十九日のお返しはかけ紙(のし紙)をかけて贈るのがマナーです。水引は黒白または関西では黄白の結び切りを選び、表書きは「志」もしくは「粗供養」とします。蝶結びの水引は何度でも結び直せることから、何回あっても嬉しい祝い事に使用されますので、弔事である法要の贈り物にはふさわしくありません。包装紙も白やグレー、落ち着いた色合いの青や緑のものを選ぶようにしましょう。菊の模様などシンプルな柄の入った包装紙でも問題ありません。引き出物を郵送する場合は、必ず挨拶状も添えるようにしましょう。

引き出物を郵送する際には、心のこもった挨拶状を添えることが大切です。挨拶状の基本的な内容としては、お供えを頂いた事に対するお礼、四十九日の法要が滞りなく済んだ報告、引き出物の品を贈らせていただいた旨を記載します。時候のあいさつは必要ありません。
挨拶状の基本構成は、
- 頭語: 「拝啓」など
- お礼の言葉: お供えや参列へのお礼
- 法要報告: 四十九日法要が滞りなく終わったことの報告
- 品物紹介: お返しの品を贈る旨の説明
- 結びの言葉: 「敬具」など
となります。
挨拶状の例文としては、以下のようなものがあります:
拝啓
この度は、故○○の四十九日法要に際し、ご霊前をお供えいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、四十九日法要も無事に執り行うことができました。心より御礼申し上げます。
つきましては、粗品ではございますが、お礼の印として同封させていただきました。ご笑納いただければ幸いです。
末筆ながら、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
敬具
令和○○年○○月
○○家
郵送で四十九日のお返しを贈る場合は、以下の点に注意しましょう。
- 法要から1か月以内に届くように手配する
- 祝い事の時期(お正月、誕生日など)は避ける
- 品物が傷まないよう、適切な梱包をする
- 挨拶状は品物の上に置く
これらのマナーを守ることで、故人を偲ぶ気持ちと参列者への感謝の気持ちが適切に伝わります。地域によって細かい習慣の違いがある場合もありますので、地元の方や親族に確認するとより安心です。
まとめ
四十九日のお返しは、故人を偲ぶ大切な法要に参列してくださった方々への感謝の気持ちを表す重要な習慣です。この記事でご紹介したポイントを押さえて、心のこもったお返しを準備しましょう。

- 四十九日のお返しには「香典返し」と「法要の引き出物」の2種類があることを理解する
- 地域や家庭の習慣を尊重し、相場は3,000円〜5,000円程度を目安にする
- 「消えもの」と呼ばれる実用的な品物が定番で喜ばれる
- 参列者の年齢や関係性に配慮した品選びを心がける
- かけ紙や包装は弔事にふさわしい落ち着いたものを選ぶ
- 挨拶状を添えて感謝の気持ちを伝える
- 計画的に準備を進め、当日や郵送のタイミングに気を配る
四十九日法要は、故人との別れを受け入れ、新たな気持ちで前に進むための大切な節目です。参列者への感謝の気持ちを込めたお返しを通じて、故人を偲ぶ気持ちを共有しましょう。
関連記事
葬祭マナーカテゴリ
- 香典返し
-
- カテゴリTOP
- 香典返しとは
- 香典返しと忌明けのあいさつ状
- 香典返しのマナーや作法について
- 香典返しの送る時期やマナーについて
- 香典返しを送る際のお礼状やマナー
- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います
- 香典返し挨拶状の文例などについて
- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて
- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント
- 香典返し「のし」について
- 香典返しの相場について
- 香典返しに商品券を選ぶメリット
- 香典返しを辞退する方法
- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー
- 香典返しの品物は何が良い?
- 香典返しでカタログギフトは失礼?
- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方
- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて
- 香典返しの時期と金額相場
- 喪家・葬儀まで
- 弔問客
- 法要・供養
- 社葬