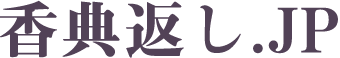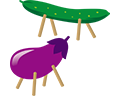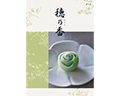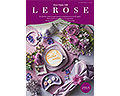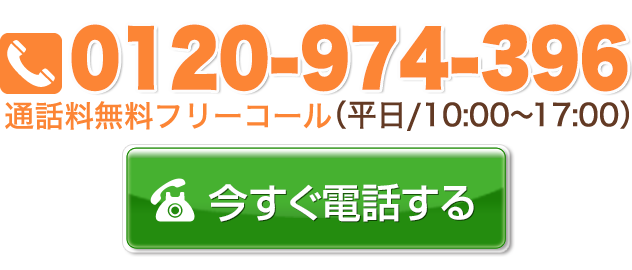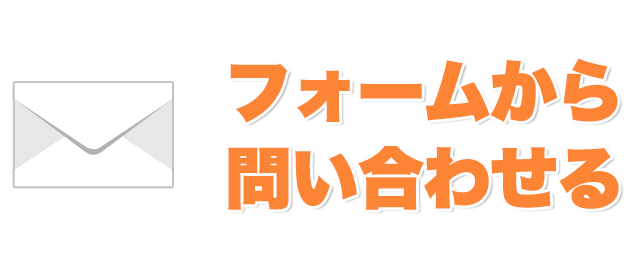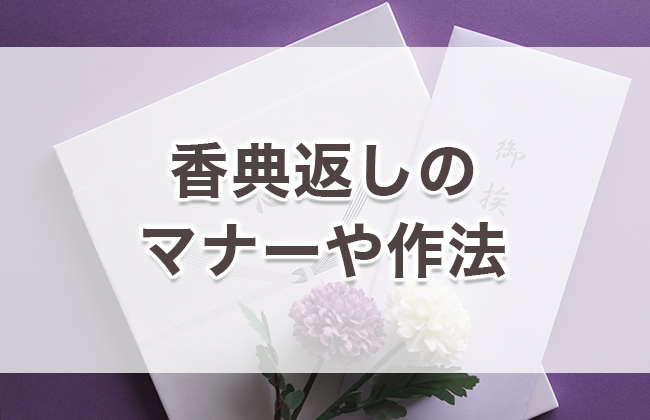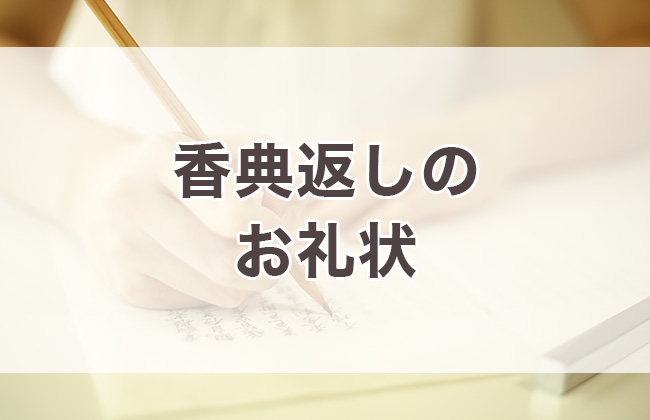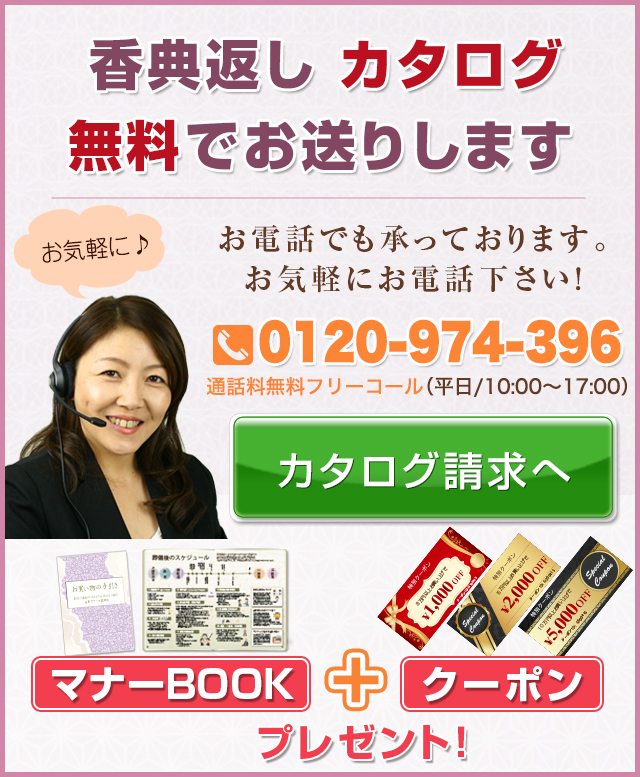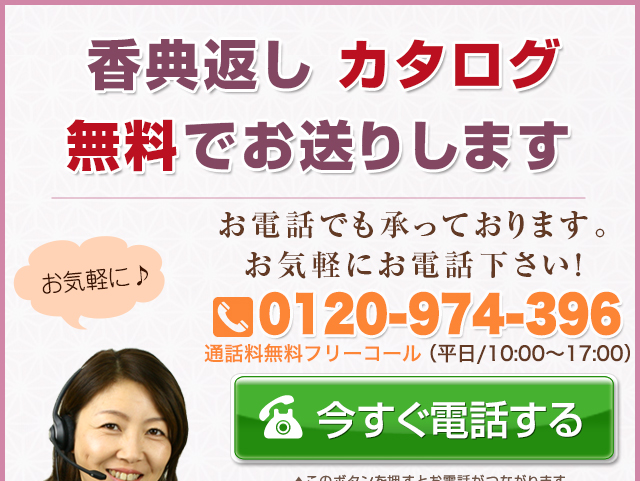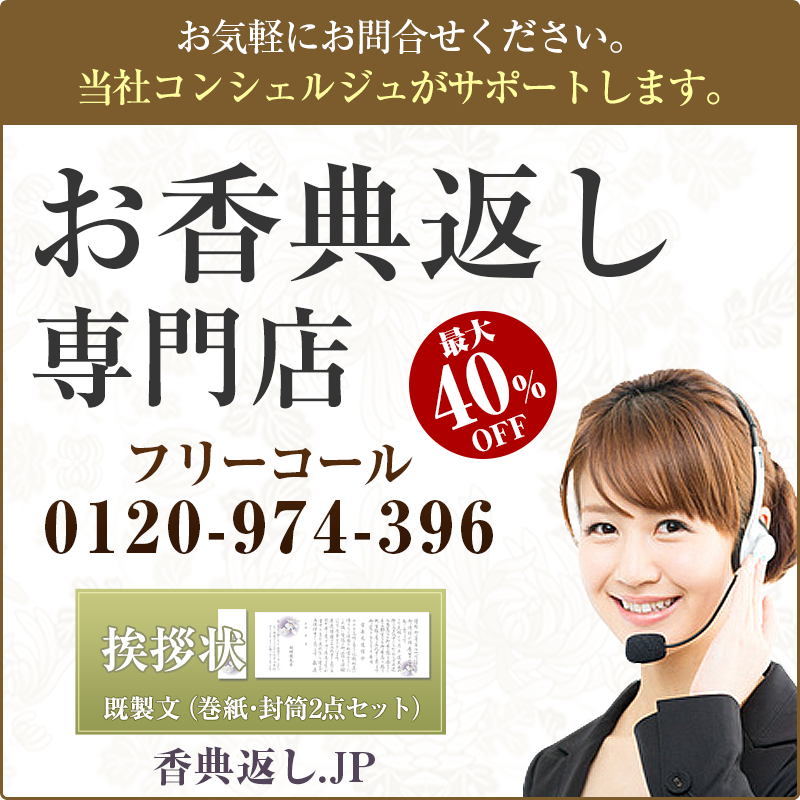香典返しに添える挨拶状には便利な定型文や代行サービスが揃っていますが、基本的なマナーを知る事は相手に感謝の気持ちを伝える第一歩。様々な場面でのお礼状にも共通しますので、ここで覚えて行きましょう。
香典返しと忌明けの挨拶状
忌明けとは?
忌明け(きあけ)とは日本の仏教における葬儀の一連の流れの中で、忌中(きちゅう)と呼ばれる喪に服する期間が終わることを指します。一般的に「四十九日」の法要をもって忌明けとなります。この期間は故人の魂が浄土へ旅立つまでの間とされており、遺族は特別な心構えで過ごすべき時期とされています。
忌明けの意味と重要性
忌明けには深い文化的・宗教的意義があります。仏教の教えでは、人が亡くなってから49日間(七七日)は、故人の魂が次の世界へ旅立つための審判を受ける期間とされています。この間、遺族は故人のために祈りを捧げ、供養することで故人の成仏を助けると考えられています。四十九日法要は「中陰法要(ちゅういんほうよう)」の最後を飾る大切な儀式であり、これを終えることで正式に忌明けとなります。忌明け後は、遺族は徐々に日常生活に戻ることが許されるという意味合いもあります。
地域や宗派による忌明けの違い
忌明けの考え方や期間は地域や宗派によって異なる場合があります。
- 仏教(一般的):四十九日をもって忌明け
- 真宗(浄土真宗):五十日目に「御斎(おとき)」と呼ばれる法要を行う地域もある
- 神道:五十日祭をもって忌明け
- キリスト教:特定の忌明けの概念はないが、一か月祭や納骨式が区切りとなることが多い
地域によっても差異があり、関東では四十九日を忌明けとすることが多いのに対し、関西では百か日(ひゃっかにち)まで忌中とする風習が残っている地域もあります。自分の地域や宗派の慣習を確認することが大切です。
忌明け後の対応
忌明け後には一般的に以下のような対応をします。
- 香典返し:葬儀でいただいた香典へのお返しを、挨拶状を添えて送る
- 墓石の建立:忌明け後に墓石の建立・納骨を行うことが多い
- 日常生活への復帰:喪服を脱ぎ、冠婚葬祭への参加や娯楽を楽しむことができる
- 忌明けの挨拶状:葬儀に参列できなかった方や、お世話になった方へ忌明けの報告と感謝の気持ちを伝える
忌明け後の対応は、故人との別れを受け入れながらも、周囲への感謝と新たな一歩を踏み出す大切な節目です。特に香典返しと忌明けの挨拶状は、故人を偲びながらも社会的なつながりを再確認する重要な儀式と言えるでしょう。
挨拶状を送るタイミング
香典返しの品物は、四十九日の忌明け後に挨拶状を添えて送るのが一般的な習慣となっています。この香典返しと挨拶状には葬儀などでお世話になった感謝の気持ちと共に、四十九日の法要を滞りなく終えることが出来たという報告の意味合いも兼ねています。従って挨拶状は香典返しの品物と共に、忌が明けたら出来るだけすぐに送るものと考えてください。
一方、最近主流となりつつある、葬儀の当日に香典返しを渡す「当日返し」の場合はどうすれば良いのでしょうか。当日返しの場合は会葬御礼品にお礼状を添えるため、特に香典返しに添えるお礼状は必要ないという考えもあります。しかし、四十九日の法要を終えた報告を兼ねていることを考えれば、忌明け後に改めて挨拶状を送るのは決しておかしなことではありません。
忌明けの挨拶状は「感謝の気持ち」と「法要を終えた報告」の2つの意味があるという事を覚えておくと分かりやすいですね。

香典返しと一緒に送る場合の注意点
忌明けの挨拶状は通常、香典返しのお品とともにお届けするのが一般的です。その際には、いくつかの点に留意することで丁寧な印象を伝えることができます。
まず、香典返しとしてお贈りする品物については文中で軽く触れておくとよいでしょう。その際には「つまらないものですが」「ささやかではございますが」といった、控えめな表現を用いるのが慣例とされております。また、いただいた香典の金額やお届けする品物の価格に直接言及することは控えるのが望ましく、返礼品はあくまでも感謝の気持ちをお伝えするものであることを意識します。
さらに、香典返しを直接お渡しできない場合には「本来であれば拝顔のうえご挨拶を申し上げるべきところではございますが」などの一文を添え、事情を説明するとより丁寧な印象を与えます。なお、香典返しの品物はいただいたご香典の三分の一から半額程度のものを目安に選ぶのが一般的です。
香典を辞退した場合の挨拶状
最近は「香典辞退」とする家族も増えています。香典を辞退した場合でも、お悔やみに来てくださった方への感謝を伝えるために挨拶状を送ることは大切です。香典辞退の場合の挨拶状では「お心づかいをいただきありがとうございました」「ご厚情に深く感謝申し上げます」などの表現を使い、香典には直接触れないようにします。
内容は定型文で良い?
香典返しに添える挨拶状には様々なマナーや書き方のポイントがあるため、定型文を参考にしながら書く方がむしろ一般的と言えるかもしれません。とはいえ、親せきや故人にとって親しい間柄の人にも、ネットで調べたありきたりな定型文の挨拶状では相手も寂しく感じるのではないでしょうか。
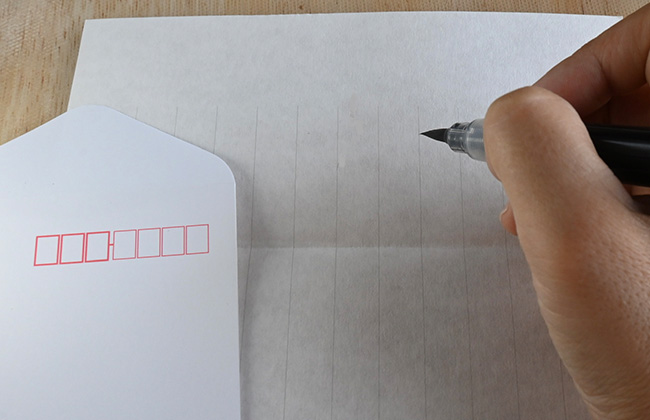
挨拶状は香典を頂いた方全てに送るものですので、送る相手によって文面を変えるのが理想です。しかし実際はなかなかそこまで手が回らないものですよね。全員に送る挨拶状は定型文を利用して印刷したもので問題ありませんが、特に親しい方には定型文とは別に、手書きの挨拶状を添えてみてはいかがでしょうか。故人の生前の人柄や思い出など相手にとって特別な文章を書き添えるだけでも、より感謝の気持ちが伝わるものですよ。
宗教別で内容は違う?
香典は仏教の香のお供えが由来とされていますが、香典や、お礼状を添えてお返しを渡すのは宗教を問わずに一般的な慣例となっています。挨拶状における注意点としては、それぞれの宗教に応じて表現を変える事が挙げられます。
「香典」や「法要」などの言葉は、仏教の表現が一般的です。それぞれの宗教に応じて、適切な表現に置き換えることが大切です。下記を参考にしてそれぞれの宗教の言葉に置き換えて下さいね。
- 仏式:「四十九日法要」「成仏」「供養」「弔問」「香典」
- 神式:「五十日祭」「帰幽」「神饌」「弔問」「御玉串料・御榊料」
- キリスト教(カトリック):「帰天」「ミサ」「弔問」「御花料」
- キリスト教(プロテスタント):「召天」「礼拝」「弔問」「御花料」
また、キリスト教や無宗教の様に忌明けという考えがない場合は「納骨を済ませたご報告」や「万事滞りなく済ませることが出来たご報告」とすると良いでしょう。
忌明けの挨拶状の書き方
忌明けの挨拶状は四十九日法要を無事に終えたことを報告すると共に、葬儀でのお悔やみやお供えに対する感謝の気持ちを伝えるものです。基本的な書き方を押さえて、心のこもった挨拶状を作成しましょう。
忌明けの挨拶状を出すタイミング
忌明けの挨拶状は、四十九日法要を終えてから1週間から10日以内に送るのが望ましいとされています。実際には法要の準備や香典返しの手配などで忙しい時期ですので、遅くとも1か月以内に送れば問題ありません。ただし、あまりに時間が経ってしまうと相手に対する礼を失することになりかねませんので、できるだけ早めに対応することをお勧めします。

挨拶状の基本的な構成要素
忌明けの挨拶状には以下の要素を含めるのが一般的です。
- 時候の挨拶:通常の手紙では入れるが、忌明けの挨拶状では省略することが多い
- 挨拶文:感謝の言葉
- 四十九日法要の報告
- 故人を偲ぶ言葉
- 結びの言葉
- 日付
- 差出人名:連名の場合は誰の名前を書くべきか注意する
特に重要なのは、感謝の気持ちと法要が無事に終わったことの報告です。この二点は必ず含めるようにしましょう。
忌明けの挨拶状で使う言葉の注意点
忌明けの挨拶状を書く際は使用する言葉に注意が必要です。弔事に相応しくない表現や忌み言葉は避けましょう。以下は避けるべき表現となっています。うっかり使用しないように気を付けましょう。
- 重ね言葉:「いよいよ」「ますます」「たびたび」など
- 死や別れを連想させる言葉:「切れる」「落ちる」「去る」「別れる」など
- 不吉な数字:「四」「九」など(読み方に注意)
- 病気や災難を連想させる言葉:「苦しい」「辛い」など
手書きで書く際の注意点
どんな場面の文章でもパソコンで入力して印刷するのが当たり前になっている現代。そんな時代だからこそ、手間を惜しまず手書きした挨拶状は、より丁寧で心がこもっていると感じられるのではないでしょうか。パソコン印刷が普及しているとはいえ、忌明けのお礼状は毛筆で奉書紙(純白で上質な和紙)に手書きするのが本来のマナーです。
- 挨拶状は忌明けの報告も兼ねているため「薄墨」ではなく「濃墨」を使用しましょう。(地域によっては薄墨を使用する場合もあります)
- 便箋は白または薄いクリーム色の無地のものを選ぶといいでしょう。奉書紙(和紙)が理想的です。
- 縦書きで書きましょう。
- 句読点は使ってはいけません。
- 「ますます」「いよいよ」などの重ね言葉や忌み言葉は使用しません。
- 時候の挨拶は使用しません。
- 「拝啓」「敬具」などの頭語と結語は両方入れるか両方入れないかのどちらかに統一しましょう。
- お礼状は一枚に収め、封筒も一重の白無地を使用します。
などが注意点として挙げられます。せっかく手書きで書くのですから、丁寧な字で心を込めて書くようにして下さいね。
家族葬の場合の挨拶状
「家族葬」とは遺族や親せきなど、ごく近しい人だけで故人を弔う葬儀の事で、近年増えてきている葬儀の形と言えるでしょう。家族葬の場合は通常の葬儀と違い、知人や職場関係者などには案内状を出さない、もしくは葬儀への参列を辞退いただくようにお伝えした上で行われます。
故人が逝去した事実を葬儀の後で知ったことで気を悪くしてしまう方もいるかもしれませんので、後日きちんとした挨拶状を送るのは大切なマナーです。家族葬の挨拶状では、無事に葬儀を済ませられた報告に加えて、家族葬のため葬儀にお呼びしなかったことや辞退して頂いたことをお詫びするのが大切なポイントになります。

挨拶状を送るのは通常の葬儀をした場合と同様、四十九日の忌明けのタイミングが最も一般的です。ただし、必ずこうしなければいけないと決められている訳でありませんので、喪中のはがきを挨拶状代わりにしてお伝えすることもあるようです。
家族葬の場合は、葬儀にお呼びしなかった方や香典を辞退した方への挨拶状が特に重要となります。葬儀後にきちんと挨拶状を送ることで、相手に対して失礼のないようにしましょう。
通販ショップを利用する際には
今では香典返しの品物を通販ショップで選ぶ方も少なくないと思いますが、通販ショップを利用すると「挨拶状を付けるかどうか」を聞かれることがあります。無料で挨拶状を作成してくれるショップも多く、何かとあわただしい葬儀後の遺族にとっては大変ありがたいサービスですよね。

一方でショップにお願いすると、決まりきった定型文で作られるというイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし、最近では内容も定型文から文章を一から自分で作成できるものまで様々で、遺族の要望に細かく応えるサービスを提供しているショップも増えてきています。
利用を考えている方は一度各ショップのサービスを確認しておくといいかもしれません。挨拶状の作成サービスは確かに便利ですが、すべてショップに丸投げしてしまうのではなく、基本的なマナーを自身できちんと理解した上で、相手に失礼にならない挨拶状の作成を依頼することが大切です。
忌明けの挨拶状の文例
様々な状況や関係性に応じた挨拶状の文例を紹介します。状況や関係性に応じて、適切なものを参考にしてください。
[一般的な忌明けの挨拶状(基本形)]
このたびは故○○の四十九日法要を滞りなく相済ませ 納骨を終えることができました
生前はひとかたならぬご厚情を賜り また葬儀に際しましては 温かなお心遣いをいただき 深く感謝申し上げます
おかげさまで 私ども遺族一同も少しずつ日常を取り戻しつつあります
ささやかではございますが 心ばかりの品をお届けさせていただきます
本来であれば拝眉のうえ ご挨拶申し上げるべきところ
略儀ながら書中をもちまして ご報告かたがた御礼申し上げます
[故人との関係性を強調した例文]
先般亡き父○○の四十九日法要を家族にて執り行い 無事に納骨を済ませました
生前は父に対しまして公私にわたり 多大なるご厚情を賜り 心より御礼申し上げます
父は常々周囲の方々とのご縁を大切にし 誠実に人生を歩んでまいりました
今後はその教えを胸に私たち家族一同精一杯努めてまいる所存です
本来であれば直接お目にかかり 御礼を申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中にて失礼をお詫び申し上げます
[家族葬を行った場合の例文]
このたびは故○○の葬儀を家族葬にて静かに執り行い 先日四十九日法要ならびに納骨を滞りなく終えることができました
ご生前に賜りましたご厚誼に対し深く御礼申し上げます
本来であれば 皆様にご参列いただき ご報告をすべきところでございましたが
事情によりご案内を控えさせていただきましたことを 何卒ご容赦くださいませ
心ばかりではございますが 品をお届けいたしますのでご受納賜りますよう お願い申し上げます
略儀ながら書中をもちまして ご報告と御礼を申し上げます
[会社の同僚・上司への例文]
このたびは故○○の四十九日法要を無事に終えることができ 納骨も相済みましたのでここにご報告申し上げます
皆様には日頃よりひとかたならぬご配慮を賜り また葬儀に際しましては温かいお言葉やお心遣いをいただき 誠にありがとうございました
故人もきっと感謝の気持ちで 皆様を見守っていることと存じます
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう お願い申し上げます
略儀ながら書中にて失礼ながら 御礼申し上げます
[参列できなかった方への例文]
このたびは故○○の葬儀に際しまして ご多用のなか弔意を賜り 誠にありがとうございました
おかげさまで 先日四十九日法要を滞りなく終えることができ 無事に納骨も済ませました
ご参列の機会を設けられなかったことは残念でございましたが 生前に賜りました温かいご厚情に深く感謝申し上げます
略儀ながら書面にて 御礼とご報告を申し上げます
[神式の場合の例文]
このたびは亡き○○の五十日祭を滞りなく相済ませ 納骨も終えることができました
御霊もようやく安らかに鎮まりましたことと存じます
生前に賜りましたご厚志に対し 家族一同心より御礼申し上げます
本来であればご挨拶に伺うべきところではございますが 略儀ながら書中にて失礼させていただきます
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
[キリスト教式の場合の例文]
このたび故○○の召天記念礼拝を滞りなく終え 無事に納骨も済ませましたことをご報告申し上げます
生前に賜りましたご厚情ならびにあたたかなお祈りに 心より感謝申し上げます
今後とも変わらぬご加護とご厚誼を賜れますよう お願い申し上げます
本来であれば拝顔のうえ 直接お伝えすべきところではございますが 略儀ながら書中にて御礼を申し上げます
[忌明け前に香典返しを行う場合の例文]
先般は故○○の葬儀に際しまして 過分なお心遣いを賜り誠にありがとうございました
まだ四十九日を迎えておりませんが 心ばかりの品をお届けさせていただきましたので ご受納賜りますようお願い申し上げます
法要の節には改めて ご報告申し上げる予定でございます
略儀ながらまずは書中にて 御礼とご挨拶を申し上げます
[葬儀から時間が経過した場合の例文]
ご報告が遅くなり大変恐縮ではございますが このたび故○○の一周忌法要を無事に終えることができました
生前に賜りましたご厚情に 改めて深く感謝申し上げます
皆様のお支えのおかげで 私どもも少しずつ 穏やかな日々を過ごせるようになってまいりました
略儀ながら書面にてご報告と御礼を申し上げます

手紙の最後に添える一言の例
最後に手書きで添える一言の例です。
- 今後とも変わらぬご厚誼とご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます
- お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りいただければ幸いです
- 季節の変わり目でございますのでくれぐれもお身体を大切にお過ごしくださいませ
連名で出す場合の注意点
忌明けの挨拶状を連名で出す場合は、以下の点に注意しましょう。
- 連名の順序:故人との関係が近い順に記載(配偶者→子→孫など)
- 「〇〇家一同」の表記:個人名を列記せず、家族全体を代表する場合
- 代表者の名前:喪主や遺族の代表者の名前のみを記載する場合
例えば「故人の妻・山田花子」「故人の長男・山田一郎」という順序で記すのが一般的です。
忌明けの挨拶状Q&A
忌明けの挨拶状に関するよくある質問とその回答を紹介します。
Q.忌明けの挨拶状は必ず出さなければならないのですか?
A.忌明けの挨拶状は故人を偲び、お世話になった方々への感謝を伝える大切な儀式です。特に葬儀に参列してくださった方や香典をいただいた方には、感謝の気持ちを表すためにも送ることが望ましいとされています。ただし、地域や家庭の事情によって異なる場合もありますので無理に従う必要はありません。
Q.喪中はがきを出した場合も忌明けの挨拶状は必要ですか?
A.喪中はがきと忌明けの挨拶状は目的が異なります。喪中はがきは年賀状を辞退する旨を伝えるものであるのに対し、忌明けの挨拶状は四十九日法要を終えた報告と感謝を伝えるものです。そのため、喪中はがきを出していても、忌明けの挨拶状は別途送ることが一般的です。
Q.香典返しと忌明けの挨拶状は別々に送るべきですか?
A.一般的には香典返しの品物と忌明けの挨拶状は一緒に送ります。これは受け取る側の利便性を考慮したものであり、別々に送る必要はありません。ただし、香典返しのタイミングで忌明け前であれば後日改めて忌明けの報告をすることもあります。
Q.忌明けの挨拶状にはどのような紙を使えばよいですか?
A.忌明けの挨拶状には白または薄いクリーム色の無地の便箋を使うのが一般的です。特に格式を重んじる場合は奉書紙(和紙)を使用します。市販の忌明け用の便箋や葬儀社やペーパーアイテムショップで取り扱っているものを利用すると便利です。
Q.忌明けの挨拶状の宛名はどう書けばよいですか?
A.宛名は敬称をつけて丁寧に書きます。例えば「山田太郎様」のように「様」をつけます。夫婦宛ての場合は「山田太郎様・花子様」または「山田太郎様ご夫妻」と書きます。会社宛ての場合は「株式会社〇〇御中」や「〇〇株式会社 △△部 □□課御中」のように記載します。
Q.当日返しをした場合でも忌明けの挨拶状は必要ですか?
A.当日返し(葬儀当日に香典返しを渡す方法)を行った場合でも、四十九日法要を無事に終えたことを報告する意味で忌明けの挨拶状を送ることが望ましいとされています。特に親しい方や、故人と深い関わりがあった方には法要の報告と共に改めて感謝の気持ちを伝えることでより丁寧な対応となります。
Q.メールやLINEで忌明けの挨拶をしても良いですか?
A.若い世代や親しい間柄ではメールやLINEで忌明けの挨拶をすることも増えていますが、正式な忌明けの挨拶状は書面で送るのが一般的なマナーです。特に目上の方やビジネス関係の方には書面での挨拶状を送ることをお勧めします。ただし、親しい友人などにはメールやLINEで連絡することも許容されつつあります。
Q.忌明けの挨拶状を送るのを忘れていた場合はどうすればよいですか?
A.忌明けの挨拶状を送るのを忘れていた、または何らかの事情で送れなかった場合でも気づいた時点で送ることが大切です。その際は「お礼が大変遅くなりましたことを、心よりお詫び申し上げます」といった一文を添えると良いでしょう。誠意を持って対応することが何よりも重要です。
Q.葬儀に参列していない方にも忌明けの挨拶状を送るべきですか?
A.葬儀に参列していなくても、弔電や供花を送ってくださった方、香典を郵送してくださった方、また葬儀後にお悔やみの言葉をかけてくださった方など、何らかの形でお悔やみの意を表してくださった方には忌明けの挨拶状を送るのが望ましいです。また、故人の友人や関係者で葬儀の連絡が間に合わなかった方にも訃報と共に忌明けの報告をすることがあります。
Q.家族葬で香典を辞退した場合の忌明けの挨拶状はどうすればよいですか?
A.家族葬で香典を辞退した場合でも葬儀に参列してくださった方や後日お悔やみの言葉をかけてくださった方には、四十九日法要を無事に終えたことの報告と感謝の気持ちを伝える忌明けの挨拶状を送ることが望ましいです。香典を辞退した旨を明記する必要はなくお心遣いへの感謝を表現すれば十分です。
以上のように香典返しと忌明けの挨拶状は故人を偲び、周囲の人々への感謝を示す大切な儀式の一つです。基本的なマナーを押さえつつ、心のこもった挨拶状を作成しましょう。

まとめ
忌明けの挨拶状は故人を偲び、周囲の人々への感謝を示す大切な儀式の一つです。基本的なマナーを押さえつつも、故人や家族の想いが伝わる言葉を選ぶことが最も重要です。形式にとらわれすぎず、真心を込めた言葉で感謝の気持ちを伝えることで相手に心が届く挨拶状となるでしょう。また、故人との思い出や生前のエピソードを添えることでより心のこもった挨拶状になります。忌明けは悲しみの区切りであると同時に、新たな一歩を踏み出す時でもあります。心を込めた挨拶状で故人への供養と周囲への感謝の気持ちを表現しましょう。
関連記事
葬祭マナーカテゴリ
- 香典返し
-
- カテゴリTOP
- 香典返しとは
- 香典返しと忌明けのあいさつ状
- 香典返しのマナーや作法について
- 香典返しの送る時期やマナーについて
- 香典返しを送る際のお礼状やマナー
- 香典のお礼と香典返しのお礼は立場が違います
- 香典返し挨拶状の文例などについて
- 満中陰志の挨拶状と香典返しについて
- 香典返しに添える手紙を書くときのポイント
- 香典返し「のし」について
- 香典返しの相場について
- 香典返しに商品券を選ぶメリット
- 香典返しを辞退する方法
- 高額な香典をいただいた時のお香典お返しマナー
- 香典返しの品物は何が良い?
- 香典返しでカタログギフトは失礼?
- 香典返し 親族(親戚)への対応の仕方
- 香典返し 会社や同僚へのお返しについて
- 香典返しの時期と金額相場
- 喪家・葬儀まで
- 弔問客
- 法要・供養
- 社葬